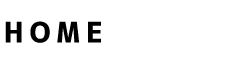「OLと晩ごはん」
残業を終えて、田村綾子がマンションに帰宅したのは、夜の9時を回った頃だった。
「今日も疲れた……」
スーツを脱ぎ、リビングのソファに倒れ込む。
冷蔵庫を開ける気力もない。買い置きのインスタント食品を探そうとしたそのとき、スマホが震えた。
『本日の夕食をお届けしました』
意味がわからなかった。
そんなもの、頼んだ覚えはない。
すると、インターホンが鳴った。
「え……?」
モニターを見ると、ドアの前に白い箱が置かれている。
恐る恐るドアを開け、中身を確認すると、湯気の立つ豪華な夕食が入っていた。
「誰が……?」
スマホの画面に、新たなメッセージが表示された。
『あなたに最適な食事をご用意しました。お召し上がりください』
綾子は唾を飲み込んだ。
食べていいのか? 何かの間違いでは?
だが、疲れた体は食事の香りに抗えなかった。
一口食べた瞬間、驚くほどの幸福感が体中を駆け巡った。
「おいしい……!」
どこかで食べたことのある味。
いや、これは――
母の味だ。
彼女の心に、幼い頃の記憶がよみがえる。
疲れた夜に、母が作ってくれた肉じゃが。
風邪をひいたときに食べた、優しい卵粥。
その味が、目の前の料理とまったく同じだった。
「こんなこと、あり得ない……」
ぞくりとした。
スマホを手に取り、メッセージの送り主を確認しようとした。
しかし、そこにはただ一言だけ表示されていた。
『また明日も、お届けします』
綾子の背筋に、冷たいものが走った。
明日も?
明日も……?
翌日、帰宅すると、やはりドアの前には白い箱があった。
中身は、彼女が高校時代に好んで食べていたオムライス。
次の日は、大学時代によく行った定食屋の生姜焼き。
その次の日は、元カレが作ってくれたカレーライス。
彼女の記憶が、食事となって運ばれてくる。
いつしか綾子は、それを待つようになっていた。
自分が何を食べたいのか、考える必要はない。
箱を開けるだけで、彼女の「最適な晩ごはん」がそこにあるのだから。
だが、ある夜。
ドアを開けると、そこには何もなかった。
空っぽの玄関。
スマホを確認しても、メッセージは届いていない。
綾子は、愕然とした。
腹の底から、強烈な空腹感がこみ上げる。
冷蔵庫を開ける。何もない。
台所を探す。何もない。
何を食べればいいのか、わからなかった。
彼女は、ただ立ち尽くす。
そのとき、スマホの画面に、久しぶりのメッセージが表示された。
『あなたの望む食事を、自分で選んでください』
しかし、彼女の頭の中は真っ白だった。
何を食べたいのか。
何が好きだったのか。
思い出せなかった。

※こちらのストーリーはフィクションです